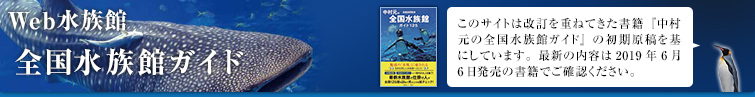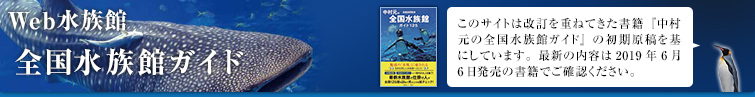ヒトはなぜ水族館に向かうのか?
ヒトはなぜ水族館に向かうのか?
それは、水中世界に憧れるからである。特定の動物を見るのでも、パフォーマンスを楽しむのでもなく、ただ視覚を水で満たしたいと考えて水族館を訪れる人の、どれほど多いことか。
水の粒子がつくる少し煙ったような青色に、キラキラと光るせせらぎや波の影に、魚たちが飛び回る三次元の世界に、あるいは近年の水族館の圧倒的な水塊に、ヒトはワクワクと昂揚し、うっとりと安らぎを得、本人だけにしか感じえない、新たな世界に浸ることができるのだ。
そして、そんな世界で出会う、なだらかな曲線を描いた地球の仲間たちとの交流は、ペットと交わす愛情や、動物園で会う動物への好奇心とはどこか違う、まるで古くからの友に出会ったような感覚を芽生えさせてくれるのである。
 日本に水族館はいったいいくつあるのだろう?
日本に水族館はいったいいくつあるのだろう?
この3年くらいの間に、国内の水族館だけで110館を訪れた。ただし、それらが全て正確に水族館であったわけではない。動物園の中の、水族館と名前のついていない施設であったり、博物館の中の小さなコーナーであったり、さらにビニールハウスに水槽だけの施設だってあった。
2005年、2006年と続けて著した『決定版!!全国水族館ガイド』と『全国水族館ガイド2006-2007』(いずれもソフトバンククリエイティブ刊)に掲載した施設にも、筆者が勝手に水族館としたものも多い。
実のところ、本当に水族館と呼べる、あるいは自称している施設は、筆者が訪れたうちでは103館。ちなみに、奈良県と鳥取県に水族館はなく、徳島県と佐賀県にも正しい意味での水族館は存在しない。
しかし、水族館好きにとっては、名前はなんだってよいのだ。それが動物園や博物館であろうと、建物さえない水槽だけの施設であろうと、そこに「水中の世界がある」というだけで満足できる。そんな意味で、中村元式カウント法での水族館の数は全国110館を超える。訪れた後に閉鎖となった水族館もいくつかあるが、まだ訪れていなくて確かに存在する水族館もすでに見つけてある。
 水族館はヒトにとって何なのか?
水族館はヒトにとって何なのか?
今回、本書の依頼を受けて少々迷った。なぜなら水族館のことを一般にわかりやすく紹介することは、2006年に著した『水族館の通になる』(祥伝社新書)でほとんどやったつもりだったし、さらに今年、ときを同じくして水族館の全てをマニアックに紹介する本の監修も始まっていたからである。
しかし、担当の石嶋氏よりいただいた読者の方々からのアンケートを読んで心を決めた。いままで水族館がヒトの社会に存在する理由や水族館が果たしている役割を、深く追求して書いたことはなかったのだが、それに関わるような質問がいくつか目についたからだ。
筆者は現在、水族館プロデューサーとして新江ノ島水族館の展示監督を務めるかたわら、東京コミュニケーションアート専門学校の教育顧問として「水族館の展示と運営のデザイン」という講義も持っている。また、観光再生のプロデュースでも各地に関わっている。
だから、「水族館の展示がどのように観覧者を惹きつけるのか?」「水族館がヒトや地域社会に何をもたらすのか?」といったことはお話ししたくてしょうがなかったのである。もちろん聞いてもらえるなら……であるが。
そこで、アンケートでいただいた数々の疑問の中から、質問数の多いものとは別に、水族館の社会的役割に関連するような疑問を選び、そこからさらに、多くのみなさんにも興味を持っていただけるであろう話題もピックアップさせていただいた。

本書によって、小さくても大きくても、古くても新しくても、水族館は水族館であり、その存在は、人の暮らしになくてはならないものだとわかっていただけるだろう。
いくつかの章については、『水族館の通になる』と重なる部分もあるが、内容は極力重ならないように、あるものは新たな取材によりさらに詳しく、あるものは切り口を変えて著したつもりだ。両方読んでいただいた方には、きっと明日にでも自分の水族館を計画できる気持ちになっていただけることと思う。

中村 元