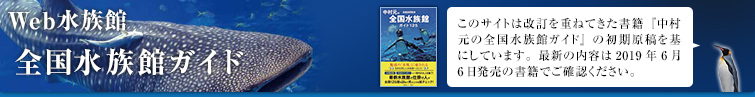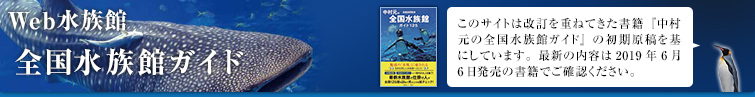中村元による「あとがき」

保育園からの帰り道、踏切のところで母親が言った「ハジメ、レールのとこに足入れたらあかんよ」。「なんで?」「足が抜けやんようになって電車にひかれるがな!」。帰宅後こっそり踏切に戻ると、そっとレールの間に足を入れてみた。そのとたん信号機が鳴りだした。びっくりして慌てたら本当に足が抜けなくなった。でも、はきものを残して足だけを抜くことができた。もちろん私は生きている。
この小さな検証で、気づいたことが2つある。まず一つは、母親の言う危険は確かに存在したということ。そしてもう一つは、危険はあったけれど電車にひかれはしなかったということだ。

子どもの頃の私は「なんで?」が口癖で、なんでも自分で確かめないことには信じられない子だった。そして今も「なんで?」が口癖だ。
私は、水族館も魚も特別に好きなわけではない。しかし、水族館プロデューサーという仕事は心から楽しんでやらせてもらっている。それは、水族館の常識に「なんで?」の種がいくらでも転がっているからだ。
水族館は子どもの教育のための施設。……なんで?
水族館は科学系博物館。……なんで?
利用者のほとんどが求めていないことを、常識としてしている商品や業界は少なくない。そしてその「なんで?」な常識は、それを提供している人々によって作られている。
だから、私の水族館プロデューサーの仕事は、新しいものをつくることではなく、利用者のための新しい常識をつくる仕事だ。スタッフと共に利用者のことを考え、古い常識を覆し新しい常識による展示を開発していく。ご想像のとおりその道は平坦ではないがとりわけ険しいわけでもない。

本書の企画をいただいた時、正直なところ心躍った。自分もたいした男になったものだと錯覚してしまったのだ。しかし、著者のやきそばかおるさんと編集の稲垣章さんのインタビューに答えているうちに、自分がたいした男ではないことが分かってきた。保育園児だった頃の「なんで?」をくり返して生きてきただけではないか。出版の直前となって読むほどに、ただただ恥ずかしいばかりである。
ただ、自らが関わった水族館はどれも、自分とクライアントがつくった子どもだと思っている。その子どもたちが成し遂げた進化を、読者のみなさんに少しでも知っていただくことができるのであれば、私の恥ずかしさなどなんのことはない、水族館プロデューサーとしての本望である。
本書がみなさんのためになんらかのヒントにもならなかったとしても、我が子である水族館にはぜひ足をお運びいただければと思う。サンシャイン水族館、おんねゆ北の大地の水族館(山の水族館)、新江ノ島水族館、鳥羽水族館、いずれも、みなさんの心になにかを伝える力を持った進化系水族館であると、それだけは自信を持ってお勧めする次第である。