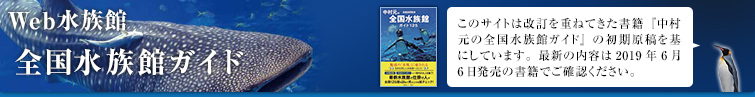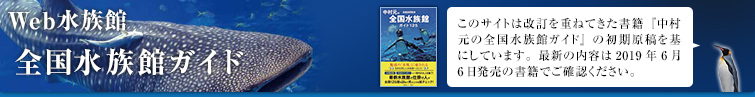「はじめに」だけ立ち読み下さい。

おいしそう! からはじめよう

中村元(水族館プロデューサー)

水族館で魚を見るとつい「おいしそう……」とつぶやいたりしませんか?
そして声に出して言ってしまったあと、「しまった! ここは水族館なんだ」とバツの悪い思いをしたことのある方もいらっしゃるでしょう。
いえいえ、けっして恥じることはありません。
それでこそ、日本人! 川や海の魚とともに暮らしてきたわたしたち日本人にとって、「おいしそう」というのは、その魚の美しさや活力を賞賛する最大級のほめ言葉なのですから。

そして、水族館の成り立ちもまた「おいしそう」という言葉に無関係ではありません。日本の水族館の多くは、水産業と非常に密接に関わっています。
東京の葛西臨海水族園のスターは、世界中から東京に集積されるクロマグロ。一方でフグの集積地・山口県の下関には、世界一多様なフグの種類を展示している海響館があります。捕鯨のまち・和歌山県の太地には、くじらの博物館という水族館があり、長崎ペンギン水族館は、長崎が捕鯨船団の基地だったため、南氷洋から鯨肉といっしょに連れてこられたペンギンが展示のはじまりです。

このような特別な例にかぎらず、日本のほとんどの水族館が、漁業の盛んな地方に建てられて、その地域で特産とされる生物の生きている姿を観察できるようになっています。
日本人にとって水族館とは、海や川の水中世界を疑似体験するとともに、ふだん食卓でいただいている魚やタコやエビなどの、生きている姿と会える場所でもあるのです。

だから水族館で、活力に満ちた美しい魚体と出会うと、ついつい「こんにちは、今日はまた一段とおいしそうで素敵になさってますね」などと挨拶してしまうというわけです。
こんなことを、わたしがうっかり隣の女性に言ったりしたらダメですが、魚やエビに対してなら大丈夫。少なくとも、水槽のなかにはわたしたちの声は聞こえません。もし聞こえたとしても魚に言葉は通じないのだから、気を悪くすることもありません。

*

そう! 言葉が通じないということも、野生生物との関係で忘れてはならないことです。
わたしたちヒトと野生生物は、話す言葉が違うだけではありません。その生い立ちも違えば、住んでいる場所も違い、それによってきっと幸せや満足の基準さえも、それぞれまったく違っているはずなのです。
激流を休みなく泳いでいる魚がいれば、穴のなかで一生暮らすエビもいます。サケは餌の豊富な広い海から生まれた川へ帰り、何も食べずにひたすら遡上し、子孫を残して安らかに死にます。
また、ヒトの感覚で気持ちいいと思うことが、魚にとっても気持ちいいわけではありません。ヒトの感情で悲しいことが、タコも悲しむようなことではありません。
「生物多様性の保全」という言葉がありますが、生物の多様性とは、種類がたくさんあるというような単純な意味ではありません。
地球上には、命の多様性、生き方の多様性、価値観の多様性などさまざまな意味での多様性が存在するということなのです。
ですから、生物の多様性を保全するということは、その無限の多様性を理解すること。ヒトの価値観や利益だけで、あるいは感情によって、地球の未来を考えてはならないという、とても深い意味を持っています。
そんな深くて重要な生物の多様性の意味が、「おいしそう」とつぶやきながら、あるいは水中世界の美しさにうっとりして浮遊感に癒やされながら、なんとなく自分で発見できる。
それが、水族館の持つ最大の価値です。
そしてこの価値は、本来は自由に生き死ぬことができたのに、水族館の狭い水槽に閉じこめられた野生生物たちへの、わたしたち人間の言い訳でもあります。

*

だから、水族館にお越しいただいたみなさんには、わたしたちがお見せする水中世界の美しさをぞんぶんに楽しんでほしいのです。
そこに息づく命の姿に、好奇心をかき立てられてほしいのです。
もちろん、魚たちをおいしそうだと思ったら、声に出して「おいしそう!」と言ってみてください。きっと彼らのことがますます好きになるでしょう。
本書では、北海道北見市にある「北の大地の水族館」を紹介します。この水族館では、生きている命が、生きている命を捕食する自然界の行動を見せる「いただきますライブ」というイベントを行っています。
北の大地の水族館の生物たちは、北海道の大地から切り取ってきた美しくリアルな水中景観のなかで、自然にいるのと同じように命を輝かせています。
そこには「おいしそう!」からはじまる、あなただけの発見があるはずです。